|
社会科 歴史の最初の授業を参観させてもらいました。
突然、掲示物が4つ、黒板に貼られました。
昔話でも始まるのか?と思っていたら、クイズがはじまりました。
人間(物を運ぶ人)、オオカミ(羊を食べてしまうが、人間がいると大丈夫)、羊(キャベツを食べてしまうが、人間がいると大丈夫)、キャベツの4つを、川の反対側まで渡してほしい。でも、1回に舟に乗れるのは2つ(人間とキャベツやオオカミと羊など)まで。さて、どうやって人間は反対側まで運ぶことができるでしょうか?
生徒の頭はフル回転。
・キャベツを投げてしまおう!
・オオカミに羊を乗せて、その上に人間が乗り、キャベツをもって渡ればいい!
・羊を連れて、キャベツを持ち、オオカミは泳がせよう!
など、様々な答えが出てきました。
その後、なぜ、このクイズを出題して考えてもらったのかを説明されました。
それは、「教科書には、結果しか書かれていない。」ということ。
でも「なぜ、そのような行動を起こしたのか?」ということが必ずある。
この【原因】⇒【結果】を授業では、すべて扱って行っていくよ、と話されました。
先ほどのクイズも、結果だけを見たら、そんなに面白く感じない。
事前に面白かった人と聞いたら、全員が面白かったと回答。
だから、結果だけでなく、原因やその行動などを扱っていくよ、と。
歴史の授業を私も受けてみたくなりました。
教頭 三浦でした。
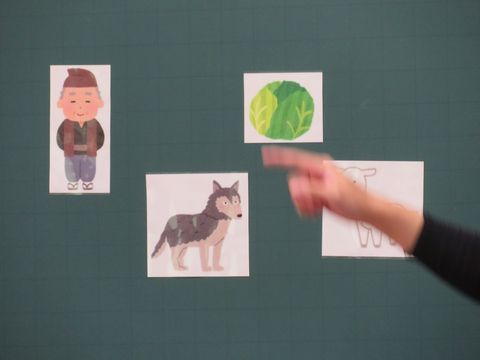
|
|